
聖剣伝説2――JRPG への情熱を芽生えさせた“ひと粒の種”
今でも消えることのない“一枚の光景”があります。
少しぼやけたブラウン管テレビ、スーパーファミコン特有の鮮やかすぎる色彩、そして画面いっぱいに現れる巨大な樹。まるで、ずっと前からそこにあったかのように。
そして遠くから聞こえてくる、不思議なのにどこか懐かしい“クジラの歌声”――他のどこでも聞いたことがないのに、なぜかすぐに分かった音。
Sommaire
あの頃の私は、ただの子供でした。エコロジーという言葉も、喪失という感情も、RPG という概念ですら、まだ知らなかった。
それでも、私の“身体”はすでに理解していたのです。
音は胸を締めつけ、画面のピクセルは自分の部屋よりも“本物”に感じられた。
そしてあの樹は、ただの背景ではありませんでした。それは“約束”だったのです。自分が知るどんな世界よりも広く、深く、謎に満ちた場所が、今まさに開かれようとしているという約束。
それが、私と 聖剣伝説2 (Secret of Mana) の最初の出会いでした。
そして気づかぬうちに、JRPG への“入門の儀式”になっていたのです。

画面の前の子供――“世界”との出会い
その頃の私は、まだ Final Fantasy に触れたことさえありませんでした。ミッドガルの近未来の街並みも、スピラの大地も、まだ知らなかった。
当時の私にとって、聖剣伝説2 (Secret of Mana) は“伝説の JRPG”なんかではなく、ただ“別の世界へ踏み出す最初の一歩”にすぎなかったのです。
最初の瞬間から、何かに強く引き込まれました。
鮮やかな色彩、そして“スタート”を押す前から物語を語り始めるようなイントロの音楽。
そして何より、手にしたコントローラーが“鍵”に変わるような感覚……。
気づけば私は、“剣を持つ少年”そのものになっていました。
選んだからではなく――“そうなるのが当然”だったのです。
頭を下げて突き進むように、後の人生でもそうしてきたように――
考えるより先に動き、ただ“進みたい”という衝動だけを頼りに前へ進んでいました。
行動ひとつひとつが儀式のようになっていきました。
走ること、ゲージが溜まるのを待って攻撃を解放すること、リングコマンドを開いて魔法やアイテムを選ぶこと。
ただの“3 つの操作”が、繰り返すうちに体に染みつき、第二の本能になりました。
今でも、私は同じリズムで書き、創っている気がします。
突き進んで、力を溜めて、そして“選ぶために一度止まる”。
感情の衝撃――仲間を失うということ
聖剣伝説2 (Secret of Mana) は、私がまだ知らなかった“喪失の衝撃”というものを教えてくれました。
終盤で、三人のうち一人が命を落とす瞬間……そんな展開を全く想像していませんでした。
それは突然で、そしてあまりにも激しかった。
単なるゲームの仕組みではありませんでした。そこにあったのは“本当の不在”でした。
緒に笑い、戦い、成長してきたキャラクターが。
あの少しズレたユーモアや強気な性格にも、いつの間にか愛着が湧いていた。
そして突然、彼はもういませんでした。
その瞬間、はっきりと理解したのです――
聖剣伝説2 (Secret of Mana) は“ただのゲーム”ではない、と。
それは、私から何かを奪い取る力を持つ“物語”でした。
ピクセルの世界の中で、本物の“喪失の空白”を感じさせるほどの力があったのです。
喪失、犠牲、そして気づき。
この 3 つの言葉が、私の心に刻まれたあの瞬間をすべて物語っています。
そして振り返れば、私はその後もずっと、この 3 つを物語の中に求め続けてきました。
JRPG は単なる娯楽ではありません――“感情の学校”なのです。
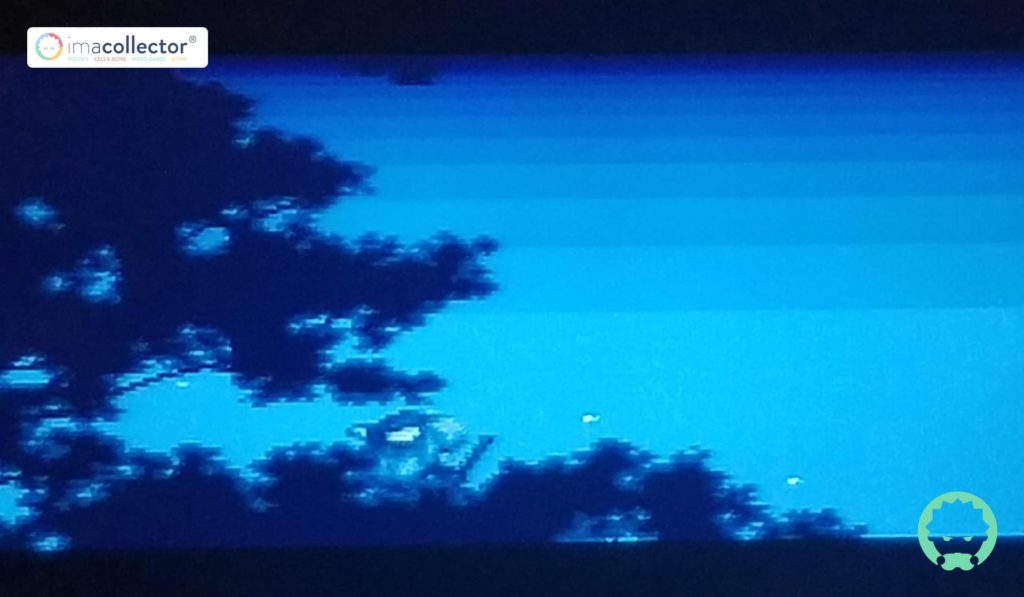

“不完全さ”という喜び
私が 聖剣伝説2 (Secret of Mana) を好きな理由のひとつは――このゲームが“完璧ではなかった”ことです。
一部のキャラクターは掘り下げが浅かった。
ボスの中には驚くほど簡単に倒せる相手もいた。
そして妙なバグもいくつかありました。
消えてしまう宝箱、入れない通路、どこかおかしい小さな違和感。
でも、まさに“それ”が魔法でした。
私は何時間も、隠された種や、孤立した町、まだ見ぬイースターエッグの存在を妄想していました。
こうした“欠けた部分”こそが、この世界に独自の個性を与えていたのです。
まるで世界そのものが、ときに制作者の手を離れて暴れ出すように。
デジタルの裏側に、どこか不安定で、手作りで、しかし確かに“人間らしい息づかい”があったように。
今でも私は、滑らかすぎる世界より、少しザラついた世界の方が好きです。
震えるピクセル、ちょっとしたバグ、うまくループしない音楽。
それらはいつも思い出させてくれます。
“想像力は完璧の中ではなく、不完全の中に根を張る”ということを。
そして、最も自分自身を投影できるのは、そんな“隙間”なのだと。

協力プレイ――“ひとつの世界”を分け合うこと
私はいつも一人で遊んでいたわけではありません。
ときどき、友達が二つ目のコントローラーを手に取ってくれました。
そしてここでも 聖剣伝説2 (Secret of Mana) は特別でした。
このゲームは“本当に”複数人でプレイできたのです。
二人目がただの“添え物”になるタイプのゲームではなく、
ここでは、たぶん人生で初めて、“一緒に進む”という体験ができました。
私を最も驚かせたのは、難易度でも戦略でもありません。“気負いがまったくなかった”ということです。
誰も無理せず、自然と役割が決まっていきました。
戦士、ヒーラー、魔法使い――それぞれが当たり前のように馴染んでいった。
競争なんてなく、そこにあったのは“静かな調和”だけでした。
もしかしたら、これは私自身をよく表しているのかもしれません。私は、努力しなくても協力が成り立ち、役割が自然に調和する世界が好きなのです。
大げさな言葉も、強い自己主張も必要なく、
ただ一緒に前へ進む――
樹の根が静かに絡み合っていくように。

今の自分に響くもの――“剣を持つ子供”と“書く大人”
今、聖剣伝説2 (Secret of Mana) を思い返すと、あることに気づきます――
私はあの“剣を持つ少年”から、本当は一度も離れたことがなかったのだと。
私は今でも、頭を下げて一直線に進んでしまうことがよくあります。
あの頃と同じ効率で、同じ“まっすぐ突き進む意志”で。
ただ一つ違うのは――その道の途中で、いくつもの夢が砕けてしまったということ。
だからこそ、このゲームは今でも深く心に響くのだと思います。
それは“信じること”“願うこと”“恐れず前へ進むこと”を思い出させてくれる。
そして――
大人になる前の私は、巨大な樹とフラミンゴの群れに心を奪われる“ただの子供”だったこと。
その驚きや感動は、大人になって身にまとったどんな防御よりも強い武器になること。
このゲームは、それを思い出させてくれるのです。
エコロジーなんて言葉の意味は、当時の私は全く理解していませんでした。
それでも“クジラの歌”だけは、確かに分かった。
マナの樹は資源ではなく、“守るべき存在”なのだと。
そして今の自分を振り返ると、あのとき震えた気持ちは間違っていなかったのだと分かります。

このゲームが“言葉抜きで”教えてくれたこと
聖剣伝説2 (Secret of Mana) から受け取ったものをまとめるなら、私はこう言うでしょう。3つの大切なことだと。
- “世界”そのものの味わい――背景ではなく、探検すべき一つの生きた世界。
- 仲間と“集団”の価値―― 互いを押しのけず、それぞれの役割のまま一緒に進むことの尊さ。
- 喪失の力―― 成長とは、消えていくもの、犠牲、そして壊れてしまう夢までも受け入れることだと気づくこと。
そしてきっと、これらすべてが今の私を形作ってきたのです。
“探り、語り、伝える”という今の生き方へと。


普遍的なまなざし――なぜ “あるゲーム” は個人的な神話になるのか
なぜ 聖剣伝説2 (Secret of Mana) は、ただの“オタク的な思い出”以上の存在なのか?
それは、このゲームが私にとって“個人的な神話”となるための 3 つの条件を満たしていたからです。
まず、音楽、色彩、効果音――そのすべてが、理解よりも先に“感覚”に語りかけてきたこと。
次に、“喪失”を通して心を揺さぶられたこと。
その瞬間、私は気づかぬうちに少しだけ大人になっていました。
そして最後に――
このゲームは、私に新たな扉を開いてくれました。
JRPG というジャンルへ、自分自身より大きな“世界の概念”へ。
どのプレイヤーにも“自分だけの 聖剣伝説2 (Secret of Mana) ”があると。
それは単なるゲームではなく、“根”のような存在。
その根は今でも、世界の見え方を静かに支え続けているのです。
結び――あの樹へ帰ること
目を閉じると、今でもあのイントロ画面が浮かび上がってきます。
巨大な樹、クジラの歌、横切るフラミンゴ、そして胸の奥を掴むあの音楽。
もう私は、あのときの“初めて出会う子供”ではありません。
“剣を持つ少年”だけでもない。
私は成長し、失い、学んできた大人です。
それでも――あの樹だけは、ずっとそこにあります。
それこそが、聖剣伝説2 (Secret of Mana) の魔法なのです。
これは、ただのゲームではありません。
それは“根を持つ樹”です。
あの樹は、子供だった私と今の私をつないでくれる。
壊れた夢や失敗がいくつあろうとも、
まだ探すべき世界があること。
まだ取り戻せる力があること。
そして遠くには、いつでも私を導くクジラの歌があることを――思い出させてくれます。
そしておそらく、この文章を書くという行為そのものが、
私にとって“あの樹の陰へ帰る旅”なのです。
プレイするたびに守りたいと思った、あの大樹のもとへ。
imacollector®によって制作された記事――日本のポップカルチャーの記憶と遺産に捧げられた編集アーカイブ。
本コンテンツは情報提供および資料目的で公開されています。すべての権利は正当な権利者に帰属します。




![『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』(スタジオディーン版・2010年)――この作品で誰もが見落としていたこと。私自身も含めて。 『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』(2010)における遠坂凛とアーチャーの公式イラスト――二人の関係性と作品テーマの分析。](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/02/imacollector-fate-unlimited-blade-works-movie-2010-deen-cover-OK-440x440.jpg)

![[分析] ワイルドアームズ オープニング考察(PS1/メディア・ビジョン)– 1996年 『ワイルドアームズ』オープニング冒頭に登場する、ページがめくられる古書。ゲームプレイに入る前に、作品の世界観と物語性を告げる象徴的な演出。](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/01/imacollector-opening-wild-arms-ps1-namco-1996-cover-OK-440x440.jpg)